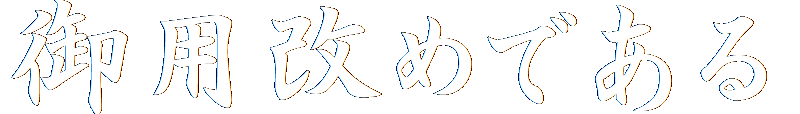新選組ゆかりの人々
近藤勇
 新選組局長として、その名を日本史に刻んだ近藤勇。彼の生誕地は武蔵国多摩郡上石原村、現在の東京都調布市ですが、新選組の歴史を語る上で、日野という地は決して切り離すことができません。なぜなら、日野こそが、新選組の精神が育まれ、多くの隊士たちの故郷となった場所だからです。
新選組局長として、その名を日本史に刻んだ近藤勇。彼の生誕地は武蔵国多摩郡上石原村、現在の東京都調布市ですが、新選組の歴史を語る上で、日野という地は決して切り離すことができません。なぜなら、日野こそが、新選組の精神が育まれ、多くの隊士たちの故郷となった場所だからです。
近藤勇は、武蔵野の大地で生まれ育ちました。彼は幼い頃から剣術に熱心で、やがて天然理心流という流派の門を叩きます。この天然理心流は、実戦的な剣術として多摩地域に広く根付いていました。農民や村人たちが身を守るために学んだ剣術であり、剣と鍬をもち、郷土を愛する多摩の人々の気質によく合っていたと言われています。
近藤勇は、その並外れた才能を見込まれ、天然理心流三代目宗家である近藤周助の養子となり、後に四代目を継承します。彼が宗家となったことで、天然理心流の名はさらに広く知られることになりました。そして、この天然理心流が、後に新選組を形成する若者たちを引き合わせる、大きな縁となるのです。
日野と近藤勇を結びつける最も重要な場所、それが日野宿の名主であった佐藤彦五郎の屋敷、通称「日野宿本陣」です。佐藤彦五郎自身も天然理心流の門弟であり、自宅には道場を構え、多くの若者が集まって剣術の稽古に励んでいました。
近藤勇は、この佐藤彦五郎の道場へ出稽古に頻繁に訪れていました。そこで彼が出会ったのが、後の新選組副長となる土方歳三です。土方歳三は佐藤彦五郎の妻の弟にあたり、日野の出身でした。他にも、剣術の天才と謳われた沖田総司、そして温厚で皆に慕われた井上源三郎など、後に新選組の中核を担うことになる面々が、この日野宿本陣で近藤勇と共に汗を流していました。
まるで磁石に引き寄せられるかのように、同じ志を持つ若者たちが日野に集い、互いに切磋琢磨し、絆を深めていきました。日野宿本陣は、彼らにとって単なる稽古場ではなく、熱い友情と忠誠心が育まれた、まさに「青春の舞台」だったのです。現在の東京都日野市に「日野宿本陣」は現存しており、当時の面影を今に伝えています。新選組ファンにとっては聖地とも言える場所で、彼らがどのような会話をし、どのような日々を過ごしたのか、想像を掻き立てられます。
文久三年(1863年)、浪士組として京都へ上ることになった近藤勇たちは、そこで後の新選組を結成します。この新選組の結成メンバーには、日野から多くの若者が加わっていました。
土方歳三、井上源三郎といった中心人物はもちろんのこと、多摩地域の天然理心流の門弟たちが、近藤勇を慕い、彼の志に共感して京都へと旅立ちました。彼らは、新選組の主要な隊士として、幕末の動乱期を駆け抜けることになります。彼らが持つ多摩の武士的精神、郷土を愛し、義に厚い気質は、新選組の強固な基盤となったと言えるでしょう。
このように、近藤勇と日野の関係は、単なる地縁を超えた深い結びつきがあります。天然理心流という共通の縁、日野宿本陣での運命的な出会い、そして日野出身の多くの隊士たちの存在。これら全てが、新選組という組織を形作る上で不可欠な要素でした。
現在、日野市は「新選組のふるさと」として、その歴史と文化を大切に守り伝えています。JR中央線日野駅近くには「新選組のふるさと歴史館」があり、近藤勇をはじめとする隊士たちの遺品や、彼らが活躍した時代の資料が展示されています。多摩地域での天然理心流の活動や、新選組結成前の隊士たちの日常など、ここでしか学べない貴重な情報に触れることができます。
また、毎年5月には、日野市最大のイベントである「ひの新選組まつり」が開催されます。新選組隊士に扮した人々が市内を練り歩く隊士パレードは圧巻で、全国から多くの新選組ファンが訪れ、当時を偲びます。
近藤勇は、日野の地で育まれた絆を胸に、幕末の激動の時代を駆け抜けました。彼の精神、そして新選組の魂は、今もこの日野の地に息づいています。私たちは、日野を訪れることで、彼らがどのような思いで時代を生きたのか、肌で感じることができるでしょう