新選組ゆかりの地
日野は甲州街道5番目の宿場町「日野宿」として栄え、多摩川の渡し場を管理する等重要拠点でした。
今もその名残を街中に見ることができます。新宿からJR中央線快速電車を利用して30分程度でアクセスできるほか、多摩都市モノレール、京王線が利用できるため、アクセスしやすい街といえるでしょう。
新選組ゆかりの地も駅周辺に集中していますので、日野の自然を満喫しながら徒歩でまわることも可能です。
日野市は子孫の方が公開している施設が多く、直接案内をしてくださいます。私設のため年中開館というわけにはいかないのでしょう。
それでも、全ての施設を同日に廻ることができるように、それぞれ開館日を合わせていただいているようで、感謝です。
今度のお休みは、日野を散策して新選組の歴史にじっくり浸ってみませんか。
それでは、ゆかりの地を具体的にひとつひとつ紹介しましょう。
上記の1日巡りではご紹介できなかったところも含め詳細にご紹介しますので、ご自分で気に入ったところも適宜組み入れてみてください。
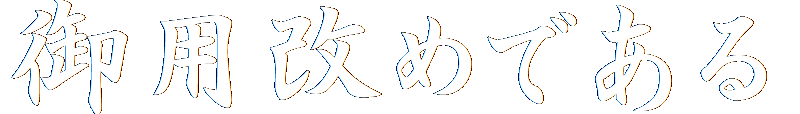
 京王線高幡不動駅からスタートし、新選組の精神的支柱であった高幡不動尊金剛寺、そして土方歳三、近藤勇、井上源三郎をはじめとする隊士たちの青春時代を育んだ日野の地を巡ります。
京王線高幡不動駅からスタートし、新選組の精神的支柱であった高幡不動尊金剛寺、そして土方歳三、近藤勇、井上源三郎をはじめとする隊士たちの青春時代を育んだ日野の地を巡ります。 八坂神社は、新選組の母体・天然理心流の奉納額がある神社です。
八坂神社は、新選組の母体・天然理心流の奉納額がある神社です。 新選組六番隊長・井上源三郎とその兄で八王子同心であった松五郎の子孫が運営する資料館で、生家の土蔵を改装した館内には、源三郎の天然理心流免許、木刀、近藤勇が松五郎に贈った刀「大和守源秀国」の他、源三郎や土方歳三の書簡、松五郎の上洛日記等の資料が展示されています。・・・詳しくはこちら
新選組六番隊長・井上源三郎とその兄で八王子同心であった松五郎の子孫が運営する資料館で、生家の土蔵を改装した館内には、源三郎の天然理心流免許、木刀、近藤勇が松五郎に贈った刀「大和守源秀国」の他、源三郎や土方歳三の書簡、松五郎の上洛日記等の資料が展示されています。・・・詳しくはこちら 宝泉寺墓地の奥まった所に井上家の墓所があります。
宝泉寺墓地の奥まった所に井上家の墓所があります。 境内には井上源三郎が学んだ寺子屋の師、文久3年(1863)8月に亡くなった千人同心日野義貴の顕彰碑が建てられており、当時新選組六番隊長だった源三郎にも知らされたのか、碑の台座の裏には、「井上源三良」と刻まれています。・・・詳しくはこちら
境内には井上源三郎が学んだ寺子屋の師、文久3年(1863)8月に亡くなった千人同心日野義貴の顕彰碑が建てられており、当時新選組六番隊長だった源三郎にも知らされたのか、碑の台座の裏には、「井上源三良」と刻まれています。・・・詳しくはこちら 日野宿本陣は、現存する建物は、佐藤彦五郎が文久3年(1863)4月に上棟し、翌元治元年(1864)12月から住み始めたものです。
日野宿本陣は、現存する建物は、佐藤彦五郎が文久3年(1863)4月に上棟し、翌元治元年(1864)12月から住み始めたものです。 日野本郷名主と日野宿問屋を務めた佐藤彦五郎の子孫が運営する資料館です。
日野本郷名主と日野宿問屋を務めた佐藤彦五郎の子孫が運営する資料館です。 新撰組と幕末維新・甲州道中日野宿をテーマとする展示施設で、日野と多摩地域の歴史と文化を紹介し、その中での新撰組の位置づけを明らかにする狙いをもって、新撰組の誕生から終焉迄の資料を展示しています。・・・詳しくはこちら
新撰組と幕末維新・甲州道中日野宿をテーマとする展示施設で、日野と多摩地域の歴史と文化を紹介し、その中での新撰組の位置づけを明らかにする狙いをもって、新撰組の誕生から終焉迄の資料を展示しています。・・・詳しくはこちら 新選組土方歳三の菩提寺高幡山金剛寺には、近藤勇・土方歳三両雄の碑や、土方歳三の銅像、又大日堂には土方歳三の位牌や新選組隊士慰霊の大位牌等、更に奥殿では歳三の書簡ほか多くの新選組資料が展示されています。・・・詳しくはこちら
新選組土方歳三の菩提寺高幡山金剛寺には、近藤勇・土方歳三両雄の碑や、土方歳三の銅像、又大日堂には土方歳三の位牌や新選組隊士慰霊の大位牌等、更に奥殿では歳三の書簡ほか多くの新選組資料が展示されています。・・・詳しくはこちら 殉節両雄とは多摩の出身で幕末の京都において勤皇の志士から恐れられた新選組の隊長近藤勇と副長土方歳三を指しています。碑文は二人の誕生から死に至るまでの略歴と功績を記して顕彰するために建立することになりました。・・・詳しくはこちら
殉節両雄とは多摩の出身で幕末の京都において勤皇の志士から恐れられた新選組の隊長近藤勇と副長土方歳三を指しています。碑文は二人の誕生から死に至るまでの略歴と功績を記して顕彰するために建立することになりました。・・・詳しくはこちら 土方歳三の生家が建て替えを機に、平成2年から自宅の一室を開放して作られている資料館です。
土方歳三の生家が建て替えを機に、平成2年から自宅の一室を開放して作られている資料館です。 土方歳三の菩提寺は高幡山金剛寺(通称、高幡不動尊)ですが、墓はこの石田寺にあり、命日の5月11日のみならず、歳三を慕う多くの参詣者が訪れています。
土方歳三の菩提寺は高幡山金剛寺(通称、高幡不動尊)ですが、墓はこの石田寺にあり、命日の5月11日のみならず、歳三を慕う多くの参詣者が訪れています。 三鷲山鶴樹院 大昌寺は1602年に創建されたお寺。新選組育ての親として知られる佐藤俊正(彦五郎)と、その妻こと、土方歳三の姉ノブのお墓があります。・・・詳しくはこちら
三鷲山鶴樹院 大昌寺は1602年に創建されたお寺。新選組育ての親として知られる佐藤俊正(彦五郎)と、その妻こと、土方歳三の姉ノブのお墓があります。・・・詳しくはこちら 日野北原とんがらし地蔵尊は、沖田総司が幼いころ、姉のみつとお参りに来ていたという伝承がある日野の地蔵尊です。赤唐辛子を供えると眼病に効くとして信仰を集めていました。・・・詳しくはこちら
日野北原とんがらし地蔵尊は、沖田総司が幼いころ、姉のみつとお参りに来ていたという伝承がある日野の地蔵尊です。赤唐辛子を供えると眼病に効くとして信仰を集めていました。・・・詳しくはこちら 今となっては碑と木が残っているだけの更地ですが、ここが土方歳三の生誕地と言われています。今の土方歳三資料館があるのは引っ越した後の場所です。・・・詳しくはこちら
今となっては碑と木が残っているだけの更地ですが、ここが土方歳三の生誕地と言われています。今の土方歳三資料館があるのは引っ越した後の場所です。・・・詳しくはこちら 日野宿交流館は、日野市が運営している観光スポットで、観光案内所も兼ねています。1階に新選組のお土産やグッズの売店兼観光案内所、2階に日野宿の歴史と新選組関係の展示があります。・・・詳しくはこちら
日野宿交流館は、日野市が運営している観光スポットで、観光案内所も兼ねています。1階に新選組のお土産やグッズの売店兼観光案内所、2階に日野宿の歴史と新選組関係の展示があります。・・・詳しくはこちら 伊十郎屋敷長屋門は、土方家の分家だった土方伊十郎の屋敷の長屋門です。土方歳三は、この門をくぐって、近藤勇からの稽古への誘いの手紙を伊十郎屋敷の久蔵(伊十郎の息子)に届けています。・・・詳しくはこちら
伊十郎屋敷長屋門は、土方家の分家だった土方伊十郎の屋敷の長屋門です。土方歳三は、この門をくぐって、近藤勇からの稽古への誘いの手紙を伊十郎屋敷の久蔵(伊十郎の息子)に届けています。・・・詳しくはこちら 石明神社は、土方歳三が生まれた石田村の隣村・新井村を守る鎮守の神社でした。石田村は多摩川の洪水で鎮守の森が流されていたため、新井村のこの石明神社が石田村の鎮守もしていました。・・・詳しくはこちら
石明神社は、土方歳三が生まれた石田村の隣村・新井村を守る鎮守の神社でした。石田村は多摩川の洪水で鎮守の森が流されていたため、新井村のこの石明神社が石田村の鎮守もしていました。・・・詳しくはこちら 石明神社の鳥居を入らず左手に進むと、浅川の堤防があります。浅川は、土方歳三が石田散薬の材料・牛革草(ぎゅうかくそう)の刈り取りをした場所です。・・・詳しくはこちら
石明神社の鳥居を入らず左手に進むと、浅川の堤防があります。浅川は、土方歳三が石田散薬の材料・牛革草(ぎゅうかくそう)の刈り取りをした場所です。・・・詳しくはこちら