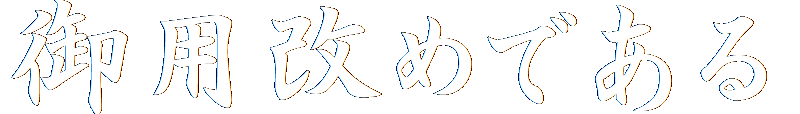新選組ゆかりの人々
馬場兵助
新選組と深い関わりを持った人物、馬場兵助(ばば へいすけ)の名は新選組の公式な隊士名簿には見当たりませんが、その足跡は幕末の動乱期を生きた多摩の若者たちの姿を今に伝えてくれます。
馬場兵助は、武蔵国多摩郡で生まれ育ちました。彼は地元の佐藤道場に通い、近藤勇や土方歳三、沖田総司らと同じく、天然理心流の剣術を学びます。その剣の腕前は確かで、日野の八坂神社に奉納された天然理心流の扁額にも、彼の名が刻まれています。これは、彼が道場でも屈指の使い手であったことを示す、重要な証拠です。
文久3年(1863年)、14代将軍徳川家茂の上洛に際し、その警護のための浪士組が募集されると、彼は試衛館のメンバーとともにこれに応じ、京都へと旅立ちます。しかし、浪士組は分裂し、一部は京都に残り、新選組を結成します。馬場兵助もまた、新選組に参加する道を選ぶかに見えました。
浪士組が分裂し、清河八郎らに従った者たちが江戸へ戻ることになった時、馬場兵助は近藤勇から京都に残るように説得されました。しかし、彼は京に残ることを選びませんでした。なぜなら、彼には故郷日野に妻と子がいたからです。彼は近藤の誘いを断り、故郷へと帰っていきます。妻子持ちであった彼にとって、新選組の厳しい規律と、いつ命を落とすかわからない生活は、家族を思う故に選択できなかったのです。この決断は、彼の誠実で家族思いな人柄を物語っています。
江戸に戻った浪士組の一部は、新徴組と名を改め、江戸市中の警備にあたります。馬場兵助もこれに加わりました。この頃、新選組の隊士募集のために江戸へ戻ってきた土方歳三と再会し、品川の釜屋まで見送りに行ったというエピソードも残っています。このことから、彼らが故郷を離れても、深い絆で結ばれていたことが分かります。
時代は明治へと移り、戊辰戦争が勃発すると、馬場兵助は新徴組隊士として、庄内藩(現在の山形県)へと赴き、新政府軍と戦いました。新徴組は最後まで幕府への忠誠を貫き、庄内藩とともに戦い続けます。しかし、敗北が決定的となると、彼は戦場で倒れることなく、庄内で開墾作業に従事し、新しい時代の到来を静かに受け入れました。
その後、明治となり故郷の日野へ戻った馬場兵助は、平穏な晩年を過ごしました。明治19年(1886年)に生涯を閉じ、彼の名は日野の欣浄寺にある石碑にも刻まれています。
最新の調査では、馬場兵助の子孫が現在も日野に暮らしており、彼の遺品や記録が大切に保管されていることが分かっています。彼は新選組の表舞台で活躍したわけではありませんが、故郷を愛し、家族を大切にしながら、動乱の時代を誠実に生きた一人の武士の姿を私たちに示してくれます。