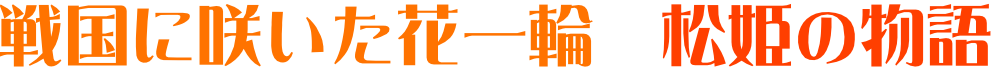松姫を慕う人々
随翁舜悦和尚
松姫の精神的な師であり、信松院の創建にも深く関わった随翁舜ト山和尚、別名「卜山禅師」または「随翁舜悦和尚」について、彼の人物像や逸話、そして松姫との関係性をご説明いたします。
戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した、曹洞宗の高僧です。彼の生涯や逸話は、松姫の人生を語る上で不可欠な要素であり、八王子地域の信仰と歴史に深く関わっています。
卜山禅師は非常に高い徳を持つ禅僧として、当時の人々から尊敬を集めていました。松姫のような高貴な身分の女性が、彼の教えを請い、出家を願ったこと自体が、彼の徳の高さを物語っています。彼の存在は、荒れ果てた世の中で心の拠り所を求める人々にとって、大きな希望でした。
逸話として、松姫が出家を願った際、卜山禅師は三度まで断ったと伝えられています。これは、出家が容易な道ではないことを示し、彼女の覚悟を試すための禅師の厳しい姿勢を表しています。しかし、最終的には松姫の深い悲しみと、武田一族や信忠の冥福を祈る純粋な願いに心を打たれ、入門を許しました。このことは、彼が単に厳しいだけでなく、深い慈悲の心を持っていたことを示しています。
卜山禅師は、120歳という異例の長寿を全うしたと伝えられています。これは、当時の平均寿命を遥かに超えるものであり、彼の健康な心身と、禅僧としての清貧な生活が反映されているのかもしれません。その長寿は、彼の徳の高さを示す伝説的な要素の一つとされています。
卜山禅師は、武蔵国楢原(現在の八王子市楢原町)の農家に生まれたと伝えられています。これは、彼が一般的な民衆の中から現れた高僧であり、特定の貴族や武家の出身ではないことを示唆しています。それにもかかわらず、高貴な身分の松姫が彼に師事したことは、彼の徳の高さと教えの深さが、身分や家柄を超えて認められていた証拠と言えるでしょう。
松姫は、武田家滅亡後、八王子の金照庵に身を寄せた後、22歳の時(天正10年、1582年頃)、八王子市下恩方町にある心源院に卜山禅師を訪ねました。
松姫が心源院に卜山禅師を訪ねた背景には、以下のような理由が考えられます。
戦乱の中で多くのものを失った松姫は、世の無常を感じ、仏教、特に禅の思想に救いを求めたと考えられます。
そして卜山禅師の名声は、八王子地域だけでなく、広く伝わっていたことでしょう。松姫は、その評判を聞きつけ、彼こそが自分の心の苦しみを救ってくれる師だと直感したのかもしれません。
心源院で卜山禅師に師事し、松姫は髪を剃り、信松禅尼(信松尼)と号しました。卜山禅師の教えは、松姫が過去の悲劇と向き合い、精神的な安定を取り戻す上で大きな力となりました。彼女は心源院で約8年間修行に励み、亡き父・信玄や婚約者・織田信忠、そして武田一族の菩提を弔う日々を送りました。
天正18年(1590年)、松姫は自身の庵を構えるべく、現在の八王子市台町の地に庵を建てます。これが後の信松院です。
この庵の創建にあたっても、卜山禅師が深く関わっていたとされます。
師として弟子の新たな修行の場を整える手助けをしたことは想像に難くありません。信松院は、卜山禅師が松姫に授けた仏道の教えが具現化された場所であり、松姫の信仰の結晶とも言えるでしょう。
卜山禅師は、松姫の人生における最悪の苦境において、彼女の精神的な支柱となり、新たな生きる道を示した恩師でした。
彼の存在なくして、松姫が信仰の道に生き、信松院を創建することはなかったでしょう。彼の教えは、八王子の地において、松姫の信仰とともに、今もなお受け継がれています。