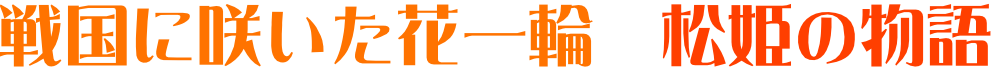松姫を思う(松姫様にかかわる様々なトピックス)

松姫様の死因は(何で亡くなったのか)
松姫(信松尼)の死因については、明確な記録は残されていません。
彼女は武田家滅亡後、八王子に逃れて信松院を開き、83歳という当時としては非常に長寿を全うしました。このことから、一般的には老衰による自然死であったと考えられています。
戦国時代という厳しい時代を生き抜き、さらに武田家滅亡という大きな苦難を経験したにもかかわらず、長寿であったことは、彼女の精神的な強さや、八王子での穏やかな生活があったことを示唆しています。
ただし、ごく一部の説や伝承、あるいは後世の創作物の中には、以下のような言及が見られることもあります(これらは一般的な歴史的事実としては認められていません)。
「病死説」ですが、具体的な病名は不明ですが、老年に伴う何らかの病気で亡くなったという推測は自然です。
「怨霊説」ですが、ごく稀に、特定の事件(例:徳川家関連の不幸)の原因として「松姫の怨霊」が囁かれた、というような記述が見られることもありますが、これはあくまで当時の一部の人々の憶測や迷信であり、松姫自身の死因を特定するものではありません。
「溺死説」ですが、ごくまれに「松姫は溺死した」といった残酷な話が聞かれたという記述がある文献も存在しますが、これは完全に根拠不明の伝聞であり、信松院の縁起や他の信頼できる史料からは裏付けられません。むしろ、松姫の評判を貶めるような意図で流された可能性も考えられます。
いずれにしても松姫研究者の間では、松姫様が八王子で信仰に篤く、地域の人々に慕われながら穏やかに生涯を終えられたという事実が重要です。その死因が老衰による自然なものであったことは、彼女の後半生が平和であったことを物語っていると言えるでしょう。
信松院には、松姫様の位牌や墓所があり、今も多くの人々が彼女の供養に訪れています。そこには、明確な死因の記録ではなく、彼女の生きた証と、後世に与えた影響の大きさが感じられます。

松姫様は美貌の持ち主であったか
松姫様は美貌の持ち主だったとされていますが、直接的に「松姫は絶世の美女であった」と明記された公式文書は残念ながら確認が困難です。当時の歴史書や軍記物は、個人の容姿よりも、その人物の行動や功績、血縁関係などを記すことが主でした。しかし、間接的な表現や逸話の中に、松姫様の美しさをうかがわせる記述が見られます。
例えば『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』は武田家の軍学書であり、歴史書としての側面も持ちます。この中には、織田信忠と松姫様の婚約の話が記されており、信長が松姫様との縁談を喜んだ様子や、その器量に言及する記述があります。直接的な「美貌」の表現ではなくても、信長という人物がその縁談を高く評価した背景には、松姫様の魅力的な人物像、ひいては容姿も含まれていたと解釈できます。
また、江戸時代には、各藩や地域の歴史をまとめた地誌、あるいは武家や公家の系譜が数多く編纂されました。これらの文献の中には、松姫様が八王子に移り住んでからの生活や、信松院の開基に至る経緯が記されており、その際に「品行方正で、容姿も優れていた」といった記述が散見されます。これらは、後世の人々が松姫様に対して抱いていたイメージを反映していると言えるでしょう。
なお、信松院に伝わる縁起や寺伝には、開基である信松尼(松姫)の生涯が詳細に記されています。これらの記録は、彼女が単なる武田家の姫ではなく、信仰心に篤く、人々に慕われた高僧であったことを強調しており、その人柄の美しさが容姿と結びついて語られる傾向にあります。
しかしながら、松姫様の生前の肖像画は、残念ながら現存していません。当時の武将の肖像画でさえ稀少であり、女性の肖像画はさらに数が少ないのが現状です。しかし、後世に作られた像や絵画、そしてその人柄をしのばせる場所から、その美しさの「イメージ」を感じ取ることができます。
その一つが、信松院の「木造松姫坐像(もくぞうまつひめざぞう)」です。八王子市台町にある信松院の本堂に安置されている木造坐像は、松姫様の姿を伝える最も具体的な「物的なもの」と言えるでしょう。八王子市指定有形文化財にも指定されており、百回忌の際に寄進されたと伝えられています。
この像は、穏やかで気品のある表情をしており、当時の人々が松姫様に対して抱いていた崇敬の念や、内面的な美しさを表現していると考えられます。実際の顔立ちを写したものではありませんが、松姫様の人間性や美徳が形として表現されたものとして、非常に貴重です。時折、特別公開される機会もあります。
また、信松院の入り口付近には、旅姿の松姫様の像が建立されています。これは、武田家滅亡後に苦難の旅を続けた松姫様の姿を表現したもので、見る者にその強い意志と気高さを感じさせます。直接的な「美貌」の表現ではありませんが、その物語性と相まって、多くの人々に松姫様の印象を強く焼き付けています。
それにしても江戸時代以降に書かれた歴史物語や、明治以降に描かれた錦絵、近年発行されている郷土史に関する書籍の挿絵などには、松姫様が描かれることがあります。これらの絵は、それぞれの時代の「美人の典型」や、松姫様の伝説に基づいた想像で描かれており、直接的な史料価値は低いものの、人々が松姫様の美しさをどのようにイメージしていたかを知る手掛かりにはなります。
例えば、信忠との悲恋をテーマにした物語では、可憐で儚げな女性として描かれることが多い一方、八王子での後半生を描いたものでは、慈愛に満ちた高僧としての威厳が表現されることもあります。
なお、文献に残らずとも、八王子地域には松姫様に関する多くの口伝や伝承が残されています。これらの話の中には、松姫様の美貌が人々を惹きつけ、多くの求婚があったこと、あるいはその美しさゆえに、戦国の世を生き抜く上で苦難も多かったことなどが語られることがあります。これらは、地域の人々が長きにわたって松姫様を語り継ぐ中で、その「美しさ」を重要な要素として認識してきた証拠と言えます。
このように松姫様の美貌は、単に外見的な魅力だけでなく、その聡明さ、気品、そして波乱の生涯を乗り越えた精神的な強さと一体となって語り継がれてきました。具体的な肖像画がないからこそ、後世の人々は、文献の記述や伝承、そして信松院の坐像に、それぞれの「松姫像」を重ね合わせ、その美しさを心の中に描き続けてきたのです。

映画やドラマでの松姫
松姫様は、その劇的な生涯と悲恋の物語から、これまで数多くの映画やドラマで描かれてきました。特に「戦国時代のロミオとジュリエット」と称される信忠様との関係は、多くの創作者の想像力を掻き立てるテーマとなっています。ここでは、代表的な5作品を取り上げ、それぞれの松姫像や描かれ方について詳しくご説明いたします。
1. NHK大河ドラマ『武田信玄』(1988年)
内容と特徴:
武田信玄の生涯を重厚に描いた作品で、松姫様はその信玄の娘の一人として登場します。
この作品では、戦国大名の娘として、家同士の政略に翻弄されながらも、運命を受け入れて生きていく姿が描かれました。
松姫の描写:
少女時代の松姫は、父信玄や兄たちに囲まれ、武田家の姫として育つ様子が描かれます。織田信忠との婚約が成立し、手紙のやり取りを通して淡い恋心を抱く姿も描写されました。
しかし、両家の関係悪化により婚約が破棄され、武田家滅亡へと向かう中で、信忠への思慕を胸に秘め、悲しみに耐える姿が印象的でした。政略の犠牲となりながらも、自らの運命を受け入れ、武田家の血筋として気高く生きようとする強さが強調されています。
当時の松姫を演じたのは香川沙美さん、少女時代は上田愛美さんでした。
2. TBS系ドラマ『おんな風林火山』(1986年)
内容と特徴:
武田信玄の五人の娘たちに焦点を当て、波乱の戦国時代を生き抜いた女性たちの愛と悲しみを描いた作品です。
特に松姫が中心となり、織田信忠との悲恋を主題とした、まさに「戦国時代のロミオとジュリエット」という側面を色濃く出した作品として知られています。
大映テレビ制作で、当時のトレンディドラマ路線も意識した演出が見られました。
松姫の描写:
主人公の一人として、鈴木保奈美さんが成人した松姫を演じました。
この作品の松姫は、政略結婚や同盟破棄によって、愛する者同士が敵味方に分かれて壮絶に戦う数奇な運命に翻弄されながらも、織田信忠への純粋な愛を貫き通そうとします。
史実に基づきつつも、よりロマンティックで情熱的な恋愛ドラマとしての要素が強調されており、視聴者の涙を誘いました。
武田家が滅亡し、信忠も非業の死を遂げた後も、彼を想い続ける一途な女性像が印象的でした。
3. NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』(2017年)
内容と特徴:
井伊直虎の生涯を軸に、戦国時代の女性たちの生き様を描いた作品です。物語の舞台が遠江(現在の静岡県西部)であり、武田家や織田家との関わりも描かれる中で、松姫も登場します。
松姫の描写:
この作品での松姫の登場は限定的ではありますが、武田家の姫として、父信玄の命により織田家との同盟の証として信忠との婚約を結ぶ様子が描かれました。
政略結婚という重い現実の中で、幼い信忠との間に芽生える淡い交流や、その後の婚約破棄、武田家の滅亡といった悲劇が、直虎の視点からも描かれています。
松姫の運命が、時代の大きなうねりの中でいかに翻弄されたかが示され、彼女の悲劇性が際立つ描写がなされました。
4. 映画『清須会議』(2013年)
内容と特徴:
三谷幸喜監督・脚本によるコメディタッチの時代劇映画で、本能寺の変後の織田家の後継者争いを描いています。
史実に基づきながらも、個性豊かな登場人物たちの人間模様をコミカルに描き、多くの観客を魅了しました。
松姫の描写:
この作品では、剛力彩芽さんが松姫を演じました。
映画の主要なテーマは清須会議であり、松姫の登場は物語の大きな軸ではありませんが、本能寺の変で亡くなった織田信忠の元婚約者として、その存在が示されます。
信忠を慕っていた純粋な姫として描かれ、彼女の登場シーンでは、信忠を失った悲しみや、その後の武田家滅亡といった背景が、彼女の表情や言動から垣間見えました。
引眉(ひきまゆ)姿も披露され、その時代に合わせた扮装も話題となりました。
5. 映画『信虎』(2021年)
内容と特徴:
武田信玄の父である武田信虎を主人公とした作品で、戦国時代における親子の相克や武田家の興亡を描いています。武田家の歴史を深く掘り下げる中で、松姫もその一員として登場します。
松姫の描写:
信虎の視点から武田家の歴史が描かれるため、松姫自身の個人的な感情や信忠との関係に深く踏み込むというよりは、武田家の一員としての彼女の存在が描かれます。武田家が滅亡に向かう中で、武田の姫としての宿命を背負い、家康からの庇護を受けながらも、その誇りを保ち続ける姿が描かれた可能性があります。
作品全体が武田家の興亡に焦点を当てているため、松姫は一族の悲劇を体現する存在として描かれることが多いでしょう。
これらの作品を通して、松姫様は単なる歴史上の人物としてだけでなく、政略に翻弄されながらも愛を貫き、困難な時代を気高く生き抜いた女性として、それぞれの解釈で描かれてきました。
特に、織田信忠との悲恋は、多くの人々の心に響くテーマであり、今後も様々な形で語り継がれていくことでしょう。

戦国版ロミオとジュリエット
松姫様と織田信忠様が「戦国時代のロミオとジュリエット」と称されることが多いのですが、その理由は、主に以下の三つの点(共通点)に集約されます。
1.敵対する家同士の許されぬ恋
シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」では、モンタギュー家とキャピュレット家という、ヴェローナを二分するほどの敵対関係にある名門の家柄に生まれたロミオとジュリエットが恋に落ちます。
彼らの愛は、両家の長きにわたる確執によって引き裂かれ、最終的に悲劇的な結末を迎えます。
これに対し、松姫様は甲斐の虎と恐れられた戦国大名、武田信玄公の娘として生まれ、信忠様は天下統一を目前にした織田信長公の嫡男でした。
武田家と織田家は、特に元亀年間以降、熾烈な勢力争いを繰り広げた宿敵同士でした。一時は甲相同盟(武田と北条)から武田と織田の同盟が模索され、その証として松姫様と信忠様の婚約が成立しました。
しかし、この同盟は一時的なものであり、両家の対立は深まり、最終的には天目山での武田家滅亡へと繋がります。
このように、敵対する二大勢力、武田家と織田家の次代を担うべき二人が、政略とはいえ結ばれるはずであったという背景は、まさに「許されぬ恋」の構図を彷彿とさせます。
2.引き裂かれた運命と悲劇的な結末
ロミオとジュリエットの愛が両家の確執によって阻まれ、それぞれの死という悲劇で幕を閉じます。
松姫様と信忠様の場合も、その運命は時代に翻弄されました。元亀4年(1573年)に信玄公が病死し、武田家と織田家の関係は再び悪化。天正3年(1575年)の長篠の戦いで武田家が大敗を喫すると、両家の同盟関係は完全に崩壊し、松姫様と信忠様の婚約は破談となりました。
そして、天正10年(1582年)、織田信長による武田家討伐が実行され、武田勝頼公は天目山で自害し、武田家は滅亡します。
この時、信忠様は武田征伐の総大将を務め、松姫様は八王子に移り住んでいました。
皮肉にも、かつての許婚が自らの家を滅ぼす側に立つという、残酷な運命を強いられたのです。
さらに、そのわずか3ヶ月後には、信忠様自身も本能寺の変において二条御所で自害するという非業の死を遂げます。
互いに生き延びることは叶わず、戦国の世の激流の中で、それぞれの家と共に悲劇的な結末を迎えた点も、ロミオとジュリエットの物語と重なります。
3.互いを想い続けたとされる純粋な愛情
「ロミオとジュリエット」の核心は、周囲の対立を超越した純粋な愛です。
松姫様と信忠様の場合、実際に二人がどれほどの愛情を育んでいたのか、具体的な史料は乏しいのが実情です。
しかし、後世の物語や伝説においては、二人が互いを深く想い続けていたとする描写が多く見られます。
特に、武田家滅亡後、八王子に落ち延びた松姫様が、信忠様からの保護の申し出を断り、尼となって信忠様の菩提を弔い続けたという逸話は、二人の間に単なる政略結婚以上の、深い心の繋がりがあったことを示唆するものとして語り継がれています。
信忠様もまた、松姫様の消息を気にかけ、保護しようとしたと伝えられています。
このように、敵対する家柄でありながらも、互いを純粋に慕い、その運命に翻弄されながらも、心の中で互いを想い続けたというロマンティックな解釈が、「戦国時代のロミオとジュリエット」という比喩を生み出す大きな要因となっています。
これらの要素が複合的に絡み合い、松姫様と織田信忠様の物語は、戦国時代の悲劇を象徴するロマンティックな悲恋物語として、「戦国時代のロミオとジュリエット」と称されるようになりました。
彼らの物語は、単なる歴史的事実を超え、人々の心に深く刻まれる普遍的なテーマ、すなわち「時代に翻弄される愛と運命の悲劇」として語り継がれているのです。

松姫は織田秀信の母だったのか
──伝承と史実のはざまで──
織田秀信、幼名を「三法師」といい、織田信忠の嫡男として知られる人物です。一般的には、信忠と塩川長光の娘との間に生まれたとされていますが、実は「松姫との間に生まれたのではないか」という説も、長く語り継がれてきました。
この説を支えるとされる主なポイントは、次のようなものです。
松姫と信忠は、武田信玄と織田信長の同盟によって、嫡女と嫡男として婚約していました。当時の有力大名同士の約束として、この婚約はきわめて重みのあるものでした。そのため、正式な結婚には至らなかったとしても、両者の間に何らかの交流があった可能性を想像する余地があります。
加えて織田秀信の生母を明確に「塩川長光の娘」と断定する一次史料は、実はそれほど多くありません。中には、「側室の子」とだけ記されていたり、「母不詳」としている史料もあり、生母の特定には曖昧さが残されています。こうした背景が、「松姫説」を支える一因ともなっています。
また、松姫が晩年を過ごした八王子や、武田家ゆかりの地域には、「松姫と信忠との間に子どもがいた」という言い伝えがわずかに残されています。もちろん、これらは民間伝承の域を出るものではありませんが、長年地域の人々によって語り継がれてきた点には、注目すべきものがあります。
それにしても政略結婚とはいえ、松姫と信忠が若い男女であったことを考えると、婚約期間中に個人的な感情が芽生えた可能性も否定はできません。その感情の延長として、密かに夫婦関係に近い絆が結ばれたのではないか、というロマンチックな想像が、この説に色を添えています。
しかし、冷静に史料と状況から検討すると信憑性には疑義が生じます。
まず第一に、松姫が秀信の母であると明記された、信頼に足る同時代の一次史料は、現在のところ存在していません。たとえば『信長公記』をはじめとする織田家関連の記録には、秀信の生母に関する具体的な記述は見当たりません。逆に、後世に編まれた系図などには「塩川長光の娘」が生母とされており、一定の信頼を得ています。
また、武田家は天正10年(1582年)に滅亡しますが、その直前までの松姫は、織田軍の追討を逃れて各地を転々としており、非常に不安定な状況にありました。もし秀信が松姫の子であれば、その出生や行動に何らかの記録が残っていても不思議ではありません。しかし、そのような記録は見つかっていません。
そして当時の婚姻慣習を踏まえると、婚約段階で実際に男女関係に至ることは極めて稀です。特に、武家の嫡男・嫡女といった高貴な身分同士であれば、正式な結婚の儀礼を経ることなく関係を持つことは、社会的に認められていませんでした。
また、秀信の生年は天正8年(1580年)とされています。松姫と信忠の婚約は元亀3年(1572年)ですが、その後すぐに信玄の死により両家は敵対関係となっています。そうした敵対関係下で、両者が密かに会い、子どもをもうけたというのは、史実として成立しにくい状況です。
一方で、信忠に仕えていた家臣・塩川長光の娘が生母であるという説は、当時の政治的背景や人間関係の中で自然に理解できます。信忠が安土にいた時期に、塩川長光の屋敷に松姫が一時身を寄せていたという伝承もあり、そこで信忠と塩川氏の縁が強まったというのは十分にあり得る話です。家臣の娘が側室となることは、当時としてはごく一般的なことでした。
このように「松姫が織田秀信の母である」という説は、ロマンにあふれた美しい物語として、地域の伝承や一部の書籍などで語られ続けています。しかし、残念ながら現存する史料や、当時の政治状況、婚姻の慣習などを照らし合わせると、この説を歴史的事実として受け入れることは非常に難しいと言わざるを得ません。
むしろ、「塩川長光の娘が生母である」とする説のほうが、総合的に見てはるかに整合性があり、現在の歴史学の主流の見解となっています。
松姫と信忠の婚約は、確かに両家の政略的な結びつきを象徴するものでした。しかし、それが個人的な情愛に発展し、子をなす関係に至ったとは、少なくとも現在確認できる史料の上では考えにくいのが実情です。
とはいえ、このような説が生まれ、語り継がれてきたということ自体、松姫という女性の存在がいかに人々の心をとらえ、歴史に余韻を残しているかを示しているのかもしれません。

松姫と八王子織物のはじまり
──織物のまち・八王子の原点をたどって──
松姫(まつひめ・1561年~1616年)は、武田家が滅亡した後、八王子へと逃れ、心源院で静かな余生を送りました。
この地での松姫の暮らしと行いが、実は、後の「八王子織物」の発展に深く関わっていると考えられています。
松姫は心源院で、武田一族の菩提を弔う傍ら、自ら機織りをしていたと伝えられています。機織りは当時の上流階級の女性にとって教養であると同時に、心を落ち着ける精神的な営みでもありました。松姫が手掛けていたのは、恐らく高品質な絹織物であったと推測されます。
松姫は、心源院の周辺に暮らす人々に直接機織りの技術を教えたとされています。当時の八王子では養蚕は行われていたものの、本格的な機織り技術はまだ未熟でした。松姫は、武田家の拠点であった甲斐国、あるいは京都などから伝わった優れた技術を八王子にもたらした可能性があります。
松姫の教えにより、里人たちは模様織りや光沢ある美しい絹地など、より高度な技術を学びました。これが、粗末な自家消費用の織物から、商品価値の高い織物へと変化する基盤となったのです。
松姫の機織りは、単なる技術的な伝播にとどまらず、地域の人々の「織物」への意識そのものを変えるきっかけとなりました。
松姫が身にまとった絹織物は、里人たちにとって憧れの対象となり、「より美しい織物を作りたい」という意欲を呼び起こしました。
また、上流階級の女性である松姫が自ら機織りをする姿は、これまで地味な手仕事とされていた織物に対する社会的評価を大きく高めたと考えられます。
こうした意識の変化は、やがて織物を「生業」として捉える感覚につながり、織物の産業化へとつながっていきます。
松姫が八王子にもたらした機織りの知識と、それに伴う価値観の変化は、江戸時代に入り急速に花開いていきました。
松姫から技術を学んだ人々やその子孫が、やがて機織りを本業とするようになり、専門職としての織物職人集団が誕生します。
八王子が甲州街道の宿場町として栄えると、人々の往来が増え、織物の需要も急増。生産された織物は江戸をはじめ各地へと出荷され、「八王子織物」として名を広めていきました。
江戸後期になると、八王子織物は「多摩織」「武州織物」と並び称される大産地へと成長し、特に丈夫で美しい光沢のある絹織物として評価されるようになります。
松姫が八王子織物に与えた影響については、残念ながら明確な一次史料は多くありません。その多くは伝承や地域の記憶に基づいています。しかしながら、以下の点はほぼ確実とされています。
ひとつには、八王子には松姫に関する多くの伝承が残されており、その中には機織りにまつわる話がたびたび登場します。これは、松姫と織物との関係が長く人々の心に刻まれていた証拠です。
そして江戸時代以降、八王子が絹織物の主要産地となったことは紛れもない事実です。その黎明期に松姫のような教養ある人物が技術を伝えたという話は、非常に納得のいく背景と言えるでしょう。
松姫は、ただの亡命者や尼僧として八王子に身を寄せたのではなく、地域の産業・文化に積極的に関わった存在として、今も地域の精神的支柱となっています。
松姫が八王子で過ごしたのは、決して華やかなものではなかったかもしれません。
しかし、彼女が残した織物の技術と精神は、後の八王子織物の基礎を築き、この地域の文化と産業に大きな影響を与えました。
その存在は、歴史上の一人物というだけでなく、八王子織物の「こころ」の源として、今も私たちの中に息づいているのです。

松姫様ゆかりの薙刀の信憑性
かつて、東京都八王子市下恩方町にある寺院である心源院(しんげんいん)に伝わる薙刀が、「松姫様が愛用したもの」として広く知られていました。特に、松姫が武田家滅亡後の苦難の中で身を守るために携帯していた、あるいは武芸に秀でていた証として語られることが多かったようです。
心源院は昭和20年(1945年)8月2日未明の八王子大空襲をうけ、本堂をはじめ建物が全焼。心源院を去る時に信松尼が心をこめて縫ったという墨染めの袈裟など貴重な品々も失われてしまいました。現在唯一残っているのは古い時代の薙刀です。刀身の長さ40.8cm、反り2.8cm。松姫さま愛用の薙刀として広く知られていました。しかし、近年、この薙刀に関する調査や専門家の見解によって、従来の「松姫様愛用」という説に疑問が呈され、新たな情報が示されています。
心源院では、この薙刀は「伝・中山勘解由(かげゆ)の夫人」が所持していたものという伝承があることを明らかにしています。つまり、寺院内部に伝わる情報としては、元々松姫のものであるとは断定していなかった、ということです。
さらに、この薙刀を刀剣鑑定士が調査した結果、以下のような見解が示されています。
まずは、下原刀(したはらとう)であることは間違いないということ。下原刀とは、武蔵国(現在の東京都八王子市周辺)の下原で、室町時代末期から江戸時代初期にかけて作られた刀剣群を指します。銘文には「武州住内記康重」とあり、天正年間(1573?1592年)の二代目与五郎康重の作とされています。この点から、確かに松姫が生きた時代に合致する可能性があります。
しかし、刀剣鑑定士の見解としては、たとえ下原刀であったとしても、「中山勘解由の夫人のもの」という伝承自体にも信憑性の疑問が呈されているとのことです。具体的には、「時代はそんなに古くない」「出来があまり良くない」といった評価も含まれていたと伝えられています。これは、刀剣としての品質や作刀時期から見て、必ずしも伝説通りの由緒を持つとは言い切れない、という見方です。
それでは、なぜ「松姫様愛用」という説が広く知られるようになったのでしょうか。
松姫の生涯は、悲劇的でありながらも、たくましく生き抜いた女性の物語として人々の心に響きました。彼女が苦難の中で身を守るために武具を携えていた、という描写は、物語性を豊かにし、人々の想像力を掻き立てやすかったと考えられます。
口頭伝承や、後の時代に書かれた文献の中で、情報が混同されたり、あるいはよりドラマティックに脚色されたりする過程で、「松姫様愛用」という説が広まった可能性も考えられます。

松姫様「ドラマ化」に向け プロジェクト発足
武田家滅亡により甲斐の国から幼い子どもを連れ八王子に逃れてきた武将の娘「松姫様」。その波乱の生涯を「ドラマ化」しようとするプロジェクトがスタートした。
発起人は八王子商工会議所女性経営者の会シルクレイズ会長、町田典子さん(同会議所副会頭)。3月24日に関係者らが集まり旭町で初めて勉強会が開かれたという。
平成28年に、松姫様が眠る台町の信松院で400年祭が執り行われたのがきっかけという。
勉強会で町田さんは「NHK大河ドラマが究極の目標。しかし大河は全国各地との競争もありハードルは高い。3、5クールのドラマや映画でもいい」と希望を述べたといいます。
ドラマ化実現にむけ「オール八王子で盛り上げていく」ため、今後同会議所の田辺隆一郎会頭を含め実行委員会を立ち上げる予定

松姫応援作戦のご案内 松姫物語「花は絶えず」
関係各位 殿
平成29年1月16日
(松姫様月命日)
松姫応援作戦のご案内
松姫物語「花は絶えず」
国の史跡に指定されている滝山城跡を始めとする、八王子の歴史や文化を多くの人たちに知ってもらい、今年市制100周年を迎える八王子を応援する、そのような目的で作られた歌を「八王子教育演歌」と呼びますが、今回「その生き方が日本人女性のお手本、鏡とも言われて多くのファンを持つ」武田信玄の息女「松姫」を題材にした「松姫物語・花は絶えず」カップリングとして「滝山城の春」この2曲を収録したCDを、市制100周年に向けて自主制作する事と致しました。ここに謹んでご案内申し上げます。
八王子教育演歌 松姫物語「花は絶えず」
歌 植松 しのぶ
八王子教育演歌 「滝山城の春」
同上
作詞作曲 猿島 渡
この歌を地元八王子出身の演歌歌手、徳間ジャパン所属の「植松しのぶ」さんにステージ等で歌ってもらい八王子市全体に広めて行き、さらに松姫ゆかりの市町村やお寺等にもご協力いただいて「松姫の生きた歴史を多くの人たちに知っていただき、音楽を通して人の輪を広げ地域を元気にし、八王子を応援、宣伝する」これらの事を「松姫応援作戦」と呼びます。趣旨をご理解いただき、関係各位の応援ご協力をお願い申し上げます。
音楽で地域を元気にする会 森下 晴男