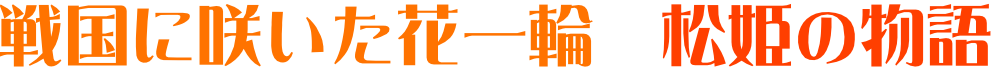松姫を慕う人々
保科正之と松姫
 保科正之が幼少期に八王子の信松院で養育されたという説は、歴史的事実として広く認められているわけではありませんが、有力な伝承として語り継がれています。この説は保科正之の生い立ちと、武田氏ゆかりの人物との深い繋がりを考える上で非常に興味深い点です。
保科正之が幼少期に八王子の信松院で養育されたという説は、歴史的事実として広く認められているわけではありませんが、有力な伝承として語り継がれています。この説は保科正之の生い立ちと、武田氏ゆかりの人物との深い繋がりを考える上で非常に興味深い点です。
この説が生まれる背景には、徳川秀忠の正室であるお江与の方(崇源院)の強い嫉妬があります。お江与の方は、秀忠が側室を持つことを非常に嫌がり、その結果、秀忠の庶子は公にされることなく、人知れず養育される必要がありました。保科正之(幼名:幸松丸)は、秀忠と乳母の侍女であるお静(後の浄光院)との間に慶長16年(1611年)に生まれた四男です。
このため秀忠は正之の存在をお江与の方に知られることを恐れ、生まれた幸松丸(正之)を密かに養育する必要がありました。
見性院は、武田信玄の次女で、穴山梅雪の未亡人です。徳川家康の庇護を受け、江戸城内に住居を与えられていました。保科正之の生母であるお静は見性院のもとに預けられ、そこで幸松丸(正之)を出産しました。
信松尼(松姫)は、武田信玄の四女(または五女、六女)で、八王子に信松院を開いた人物です。見性院とは姉妹にあたるわけです。
一部の資料や伝承によると、見性院と姉妹である信松尼(松姫)が八王子に開いた信松院に、幼い幸松丸が預けられ、5歳頃まで養育されたとされます。信松院は、戦乱で傷ついた人々を癒やし、武田家旧臣たちの心の支えとなった寺院であり、そうした縁で幸松丸が託されたと考えられています。
そして5歳、または7歳になった幸松丸は、信州高遠藩主・保科正光の養子となります。これは、徳川家の意向を受けた土井利勝や井上正就らの老中を通じて行われたもので、保科氏では家督を継ぐべき実子がいたにも関わらず、廃嫡して幸松丸を養子に迎えたとされています。
しかしながら信松院に保科正之が養育されたことを直接的に示す江戸時代の確たる史料は、現在のところ見つかっていません。このため、あくまで「説」や「伝承」として扱われています。
一方、保科正之の生母お静が見性院のもとに預けられていたことは広く知られており、見性院と信松尼が姉妹であることから、両者の間で連携があっても不自然ではありません。
信松尼が武田家旧臣や地域の人々に慕われ、頼りにされていたことは事実であり、そのような人物が将軍の隠し子の養育に関わってもおかしくはありません。
そして八王子には信松院があり、正之の出生地とされる江戸から比較的近い距離にあります。
この信松院での養育説は、保科正之の生い立ちにまつわる「秘匿性」と「武田家との縁」を象徴する重要なエピソードとして捉えています。例え厳密な意味での史実として断定できなくても、当時の人々が、将軍の隠し子が武田家の血を引く尼僧によって密かに養育されたという物語に、ある種の真実味やロマンを感じ、語り継いできた背景があると考えます。
保科正之が後に会津藩主として幕閣の重鎮となり、その生涯において「筋の通らないことは一切認めない」という強い意志と清廉潔白な性格を示したことは、彼の幼少期の複雑な境遇と、彼を養育した人々(見性院や信松尼など)の思想や生き様が影響している可能性も十分に考えられます。この説は、保科正之という人物の多面性や、徳川家と旧武田家の複雑な関係性を理解する上で、非常に示唆に富むものと言えるでしょう。