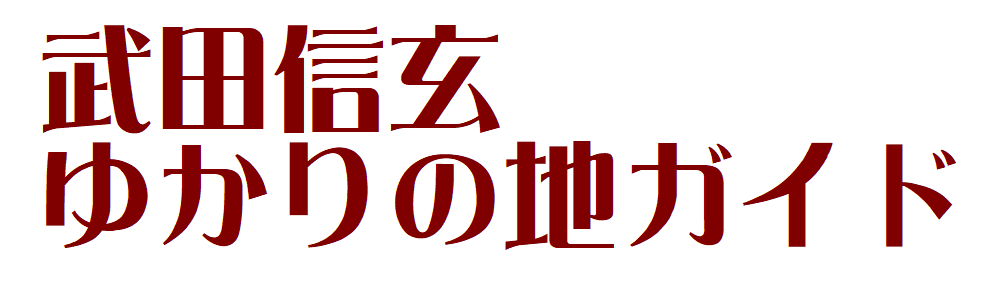武田信玄、若き日の苦闘武田信玄の生涯



武田信玄、若き日の苦闘
永禄16年(1521年)、後の武田信玄、幼名・太郎が甲斐国に生を受けました。
彼は、甲斐の守護である武田信虎の嫡男として、武田家の未来を担う存在として期待されていました。
しかし、彼の幼少期は決して平穏なものではなく、その波乱に満ちた生涯は、生家である武田家の中で、実の父との激しい確執から始まったのです。
信玄の人生を語る上で、この誕生から幼少期にかけての出来事は、彼の人間形成と、その後の治世に大きな影響を与えました。
信玄誕生と「甲斐の狂虎」
信玄が生まれた永禄16年は、甲斐国にとって激動の時代でした。
この前年にあたる永禄15年、甲斐は宿敵・今川氏との間で激しい戦いを繰り広げ、信虎は自ら指揮を執り、今川軍を撃退しました。
信玄の誕生地とされる躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)の詰城である要害山城で生まれたという逸話は、戦乱の最中に生まれた信玄の宿命を象徴しているかのようです。
父である信虎は、非常に優れた武将でした。戦国乱世の荒波の中で、分裂していた甲斐国内の有力国衆たちを武力で平定し、長らく内紛に悩まされていた武田家を統一しました。
彼の武勇は、「甲斐の狂虎」と恐れられるほどでしたが、その一方で、彼は冷酷で残忍な一面も持ち合わせていました。
気に入らない家臣は理由なく粛清し、領民には重い負担を課すなど、その苛烈な統治は、次第に家臣や領民の信頼を失わせていきました。
晴信を疎んじた理由
父子の確執の深化 信虎の冷酷さは、実の息子である太郎(後の晴信)に対しても向けられました。信虎は、嫡男である晴信を疎んじ、その弟である信繁(のぶしげ)を溺愛していたと伝えられています。この父子の確執には、いくつかの理由が考えられます。
まず、ひとつには、信虎は、自身の強引なやり方に反発する者や、自身の思い通りにならない者を許さない性格でした。成長するにつれて、聡明で思慮深くなっていった晴信は、父の強権的なやり方に従順ではなかったのかもしれません。
また、信虎自身が、父・武田信縄との間で家督をめぐる争いを経験しています。信虎は、同じような争いが将来的に起こることを懸念し、あえて信繁を重用することで、晴信の力を抑えようとしたのかもしれません。
そして、信虎が武田家を統一する過程で、多くの苦労を経験したのに対し、晴信は比較的安定した環境で育ちました。
信虎は、晴信の育ちの良さが、武将としての非情な決断力を欠くことになると危惧したという見方もあります。
こうした背景から、父子の関係は修復不可能なくらいにまで悪化し、武田家は内部分裂の危機に瀕するほどの大きな問題となっていったのです。
晴信の成長
晴信の才能と家臣団の支持 しかし、信虎が晴信を疎んじた一方で、晴信は幼い頃から非凡な才能を見せていました。
彼は学問に励み、特に『孫子の兵法』をはじめとする兵法書に強い関心を持っていました。
また、父とは異なり、家臣の意見を尊重し、彼らとの信頼関係を築くことに長けていました。
信虎の暴政に不満を抱いていた重臣たち、特に板垣信方(いたがきのぶかた)や甘利虎泰(あまりとらやす)らは、信虎に代わる新しい当主として晴信に期待を寄せるようになりました。
彼らは、晴信が武田家を安定させ、発展させるための唯一の希望だと考えたのです。
この幼少期の経験が、後の信玄の「人は城、人は石垣、人は堀」という哲学の原点になったと考えられます。
信玄は、物理的な城を築かずとも、家臣や領民の心という見えない城を築くことが、真の強さにつながると悟ったのです。
信玄の波乱に満ちた生涯は、この父との確執という、内なる戦いから始まりました。この経験が、彼を単なる武将ではなく、優れた為政者、そして「人」を活かすリーダーへと成長させていったのです。