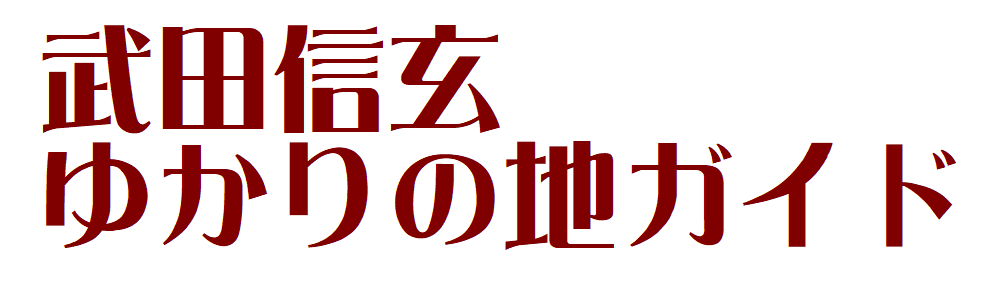甲斐善光寺甲府・甲斐国



甲斐善光寺
武田信玄公が治めた甲斐の国(現在の山梨県)に今も息づく、武田家ゆかりの地を巡る旅へと皆様をご案内したいと思います。
今回は、信玄公の信仰心と文化人としての側面を物語る、甲斐善光寺について、その歴史と信玄との深い関係を詳しく解説します。
甲斐善光寺:戦火から文化財を守る
甲府市に堂々と建つ甲斐善光寺は、戦国時代の武将である武田信玄公が建立した寺として知られています。
この寺の創建には、信玄公の深く篤い信仰心と、文化財を守ろうとする強い意志が込められていました。
戦国時代は、寺社も戦火に巻き込まれることが珍しくありませんでした。
信玄公は、宿敵である上杉謙信との川中島の戦いが激化する中で、長野の信濃善光寺が戦火で焼失するのを深く憂慮しました。
彼は、仏教の重要な文化財を後世に残すため、信濃善光寺のご本尊や宝物を、自らの領地である甲斐に移すことを決意します。
こうして、永禄元年(1558年)に、甲斐善光寺が創建されたのです。
信玄と甲斐善光寺の深い関係
甲斐善光寺の創建は、単に寺を建てるという行為以上の、深い意味を持っていました。
それは、信玄公の多面的な人柄と、彼が目指した国家のあり方を示しています。
1.信仰心と文化人としての側面
信玄公は、臨済宗の禅僧である快川紹喜(かいせんじょうき)を深く尊崇するなど、禅宗に深く帰依していました。彼は、戦乱の世にあって、人々の精神的な支えとなる信仰を非常に大切にしました。
甲斐善光寺の建立は、彼の信仰心の表れであると同時に、戦火から文化財を守ろうとした文化人としての側面を物語っています。
信玄公は、戦場で多くの命を奪う一方で、文化や芸術を重んじ、人々が心豊かに生きられる国づくりを目指していました。
このことは、彼が単なる武力による支配者ではなく、精神的な豊かさを重んじる、深い哲学を持った人物であったことを示しています。
2.「御身代わり本尊」の伝説
甲斐善光寺の本尊は、信濃善光寺と同一であるとされており、「御身代わり本尊(おみかわりほんぞん)」と呼ばれています。
これは、本尊が戦火を避けるために、自らの意思で甲斐に身を移したという伝説に由来します。
信玄公は、この本尊を甲斐に迎えることで、仏の加護を得て、戦乱の世を生き抜こうとしたのかもしれません。
また、甲斐善光寺の本堂は、織田信長や豊臣秀吉の時代に焼失しましたが、徳川家康の庇護のもと再建されました。
これは、信玄公の功績が、敵対していた徳川家にも認められ、受け継がれていたことを示しています。 現代に伝わる甲斐善光寺の魅力 甲斐善光寺は、現在も多くの参拝客が訪れる、山梨県を代表する古刹です。
特に、本堂の地下には「戒壇巡り(かいだんめぐり)」があり、真っ暗な通路を進み、ご本尊の真下にある錠前を探し当てることで、ご本尊と縁を結ぶことができるとされています。
この体験は、信玄公が戦乱の中で求めた、心の安寧を今に伝えているかのようです。
また、甲斐善光寺には、本堂を支える柱に釘が一本も使われていないという、独特の建築様式も残されています。
これは、地震の多い甲斐の地で、建物の耐久性を高めるための工夫であり、信玄公が建築技術にも深い知識を持っていたことを示唆しています。
このように甲斐善光寺は、武田信玄が戦乱の中で築き上げた、文化と信仰の遺産です。
この寺を訪れることは、単なる歴史探訪ではありません。それは、戦の天才でありながら、文化を深く愛し、人々の心を大切にした信玄公の、もう一つの顔に触れる貴重な体験なのです。
ぜひ、甲斐善光寺に足を運び、信玄公が戦火から守ろうとした文化の息吹と、彼の深い信仰心を感じてみてください。
住所: 山梨県甲府市善光寺3-36-1
公共交通機関でのアクセス :
公共交通機関では、バスを利用するのが便利です。
JR甲府駅からのアクセス :JR甲府駅南口のバスターミナルから、山梨交通バスに乗車します。
善光寺・山梨英和大学方面行きバス:この路線を利用し、「善光寺」バス停で下車します。所要時間は約15分から20分です。バス停からお寺までは徒歩数分です。
車でのアクセス :
車で向かう場合は、中央自動車道の一宮御坂インターチェンジ(IC)または甲府昭和インターチェンジ(IC)を利用するのが一般的です。
一宮御坂ICからのルート: インターチェンジを降りた後、国道20号線(甲府バイパス)を西へ進みます。大里交差点で左折し、県道3号線を北上すると甲斐善光寺に至ります。所要時間は約20分です。
甲府昭和ICからのルート: インターチェンジを降りた後、国道20号線(甲府バイパス)を東へ進みます。上今井交差点を右折し、県道3号線を北上すると甲斐善光寺に至ります。所要時間は約25分です。
駐車場: 甲斐善光寺には、参拝者用の無料駐車場が完備されています。