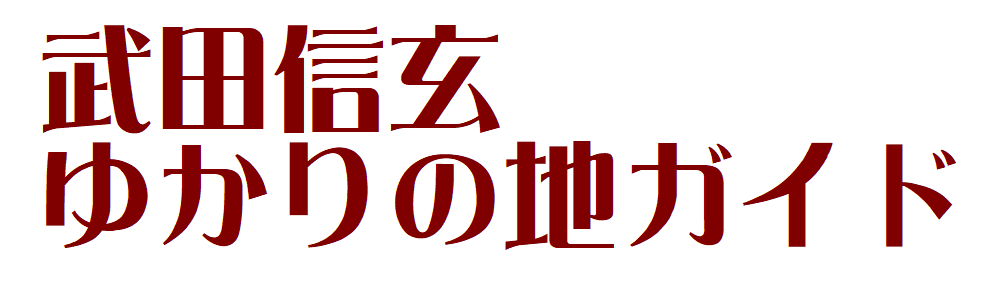典厩寺(長野市)信濃国



典厩寺(長野市)
武田信繁公の墓所について詳しくご説明いたします。
武田信繁公の墓所が複数存在する背景には、彼の壮絶な最期と、家臣たちの深い忠義の物語が隠されています。
武勇と知略を兼ね備えた名将、武田信繁
武田信繁公は、武田信玄公の実弟であり、兄を支える副将として武田家臣団の中でも絶大な信頼を集めていました。
彼はただ武勇に優れるだけでなく、教養にも深く、『信玄家法』の制定にも関わったと言われる文武両道の人物でした。
信玄公が当主の座に就く際、信繁公が家督を譲り、兄に生涯忠節を尽くしたことから、その清廉な人柄がうかがえます。
そんな信繁公の最期は、戦国史上最大の激戦の一つ、第四次川中島の戦いでした。
永禄4年(1561年)、武田軍が上杉軍の奇襲によって総崩れとなる中、信繁公は退却する本隊の殿(しんがり)を務め、自ら槍を振るって敵を食い止めました。
しかし、激しい戦闘の中で壮絶な討ち死にを遂げました。
典厩寺(長野市)に眠る遺体
武田信繁公の遺体は、討ち死にした戦場である現在の長野市に埋葬されたと伝えられています。
そして、その地に建立されたのが典厩寺(てんきゅうじ)です。
典厩寺の由来:
寺の名前は、信繁公の官職であった「左馬助(さまのすけ)」の唐名である「典厩」に由来します。
寺の建立:
信繁公の死から数十年後、松代藩主となった真田信之(真田幸村の兄)が、武田家への敬意と、敵味方を超えた武将の生き様を称え、信繁公の菩提を弔うためにこの寺を建立しました。
典厩寺の墓所は、信繁公の命が尽きた場所であり、戦国の世の悲劇を今に伝える重要な史跡です。
小諸市に残る首級の墓碑
一方、武田信繁公の首級は、家臣によって故郷である信州小諸市に持ち帰られ、布引山釈尊寺に埋葬されたという伝承があります。
家臣の忠義:
戦国時代、主君の首級は名誉を象徴するものであり、敵に奪われることは最大の恥とされていました。
信繁公の家臣たちは、命がけで主君の首級を戦場から奪還し、故郷へと持ち帰りました。
歴史的意義:
この墓碑は、武将の遺体と首級を別々に扱う当時の慣習、そして主君に対する家臣たちの強い忠義を物語っています。
この二つの墓所を巡ることは、川中島の戦いの凄惨さ、武田信繁という人物の偉大さ、そして彼に仕えた家臣たちの深い絆を体感することにつながります。
武田信繁公の墓所が複数あるのは、戦場で倒れた「遺体」と、忠臣によって故郷に持ち帰られた「首級」という、それぞれの歴史を物語っているからです。
典厩寺(長野市): 川中島の戦場に残り、敵味方から敬意を払われた遺体の墓所。
布引山釈尊寺(小諸市): 家臣の命がけの忠義によって故郷に帰った首級の墓碑。
これらの場所を訪れることは、単に歴史的建造物を見るだけでなく、戦国武将たちの生き様や、その死にまつわる人間ドラマを深く感じることができる貴重な経験となるでしょう。
典厩寺(長野市)へのアクセス
住所: 長野県長野市篠ノ井杵淵1000
公共交通機関: JR長野駅からアルピコ交通バス「松代行」に乗車し、「水沢典厩寺」バス停で下車、徒歩約8分です。
車: 上信越自動車道長野ICから車で約3分です。
小諸市にある信繁公の墓碑へのアクセス
住所: 長野県小諸市大字大久保
アクセス: JR小諸駅からタクシーで約10分です。 武田信繁公の墓所は、川中島の戦いの悲劇と、信玄公の弟としての忠節を物語る重要な史跡です。甲斐の地から少し離れていますが、武田氏の歴史を深く知る上で、ぜひ訪れていただきたい場所です。